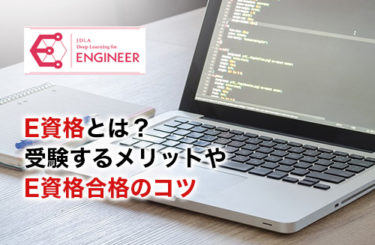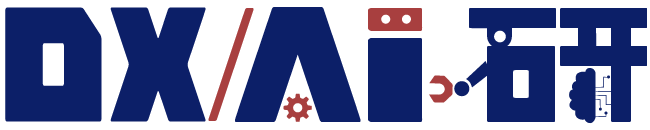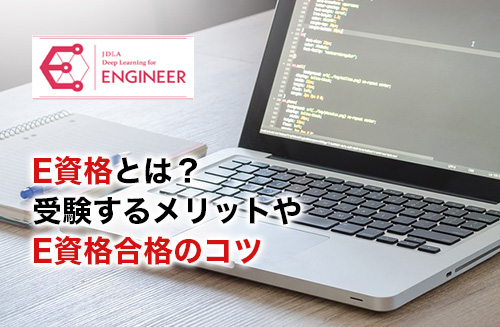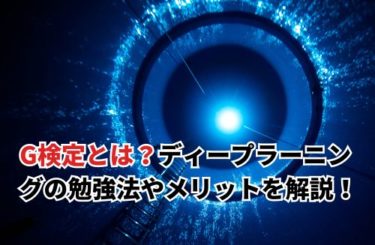E資格という検定を耳にすることも多くなってきたかと思いますが、今回は就職や転職にも有利になるE資格について、実際にどんな資格なのか、「E資格」の概要と勉強方法について解説します。
E資格を受けてみたいけど具体的にどんな資格なのか、便利なのかどうかを知りたい人はぜひ参考にしてください。
E資格とは?
まずはE資格とはどのような資格なのかを見ておきましょう。
「E資格」とは、日本の産業競争力の向上を目指し、エンジニアがAIを軸にした技術を高めるために「一般社団法人日本ディープラーニング協会」(JDLA)が創設した民間資格の資格試験です。2024年現在、E資格のような資格は日本以外には存在せず、世界初のAIエンジニアの資格となっています。
「E資格」の「E」はエンジニア(Engineer)の略であるため、ディープラーニングを実装するためのエンジニアの技能を認定する、AIエンジニア向けの資格だということができます。
公式サイトには、「ディープラーニングの理論を理解し、適切な手法を選択して実装する能力や知識を有しているかを認定する」とあります。
E資格を取得する目的
E資格はAIをただ理解しているのではなく、AIを使った技術や製品の開発ができるエンジニアの創出を目標として作られています。E資格は基本的な情報技術についての知識があるエンジニア向けの資格で、E資格試験に合格した人が認定を受けることができます。
E資格を取得すると、AIを使った開発に携わるための基礎的な情報技術、AIに関する知識、AIプログラミングに必要な理解を一通り身につけていると判断してもらえるようになるのが魅力です。
つまり、E資格の取得を通して、実践的にAI技術を使った開発に専門的に取り組める力を身につけることが可能であり、AIエンジニアとして就職や転職を考えている方や、すでにエンジニアとして勤務していてディープラーニングについてもっと深く理解したい方に人気の資格試験です。
これからAIエンジニアとして活躍していきたい人にとっては、一人前と自他共に認める人材になるための登竜門とも言えるでしょう。
今後のAIへの期待も大きくなっていることから、エンジニアの間でも人気が高い資格の一つです。
「G検定」と「E資格」の違い
日本ディープラーニング協会では、AI技術の中でも特に重要視されているディープラーニングについて、知識や技術を持っている人材の創出を目指して様々な取り組みを行っています。
E資格はその取り組みの一つで、ディープラーニングに基づく技術開発や、実装能力を持つエンジニアの創出を目指して作られた資格です。
日本ディープラーニング協会では「G検定」という検定の認定も行っており、こちらもディープラーニングに関わる知識や技術を持っている人に対して与えられています。
「G検定」の「G」はジェネラリスト(Generalist)の略であるため、ディープラーニングの基礎知識をもって、適切にAIを事業に活用する能力や知識を有しているかを検定する試験となっています。そのため、部署や役職、文系・理系を問わず、広く一般の社会人向けで、AIを使ったビジネスを展開できる人材を育てることを目指しています。
昨今のAI技術の進展と社会の課題解決への応用の必要性を考慮すると、AIに関する専門知識を持って取り扱える人材が必要になっていると考えられます。
なお、G検定とE資格は、「検定」と「資格」という言葉で明確に分けられています。
一般的に「検定」は専門的な知識や技能レベルの程度を認定するもので、「資格」は合格することで一定の権利が付与されるものと規定されています。
現時点ではE資格を持っていないと従事できない仕事はないですが、今後そのような位置づけになることも考慮して、「検定」と「資格」と分けられています。
間違っても「G資格」や「E検定」と呼ばないように気をつけましょう。
AIに関する幅広い知識を問われるG検定と異なり、E資格はプログラミングや応用数学など実践的な内容が問われるため、難易度としてはE資格のほうが高いものとなっています。
そのため、G検定を受けたことがなく、これからAIについて学ぶという方は、まずG検定合格を目指して学習を進めると良いかもしれません。
G検定とE資格は、出題される範囲は、7割~8割程度は同じ範囲で、知識レベルの深さが違うと思っていただくと分かりやすいです。G検定ではアルゴリズムの名前しか出題されないような問題も、E資格ではどのような仕組みでどのような数式で表されるかなども問われることとなります。
G検定については、下記の記事で詳しく説明していますので、興味がある方はこちらもご確認ください。
E資格の試験概要
ここからは実際にE資格の試験がどのようなものかを詳しく見てみましょう。
受験資格 | JDLAの認定プログラムを試験日の過去2年以内に修了していること |
開催日 | 年2回/2月・8月(2024年現在) |
申込み可能日 | 受験日前日の午後11時59分まで |
試験会場 | 全国の指定試験会場から会場を申し込み時に選択 |
試験時間 | 120分 |
試験問題 | 100問程度
|
受験料 (税込) | 一般 33,000円/学生 22,000円/JDLA正会員・賛助会員 27,500円 |
合格基準 | 非公開(目安として正答率65%程度で合格) |
E資格の受験資格
E資格試験を受験するには、JDLAが認定したプログラムの受講を修了する必要があります。
E資格に受かりたい!と言って受験しに行っても、JDLA認定プログラムを受けていないと試験を受けることさえできません。なぜこのようなプログラムの受講が必要なのでしょうか。
JDLAでは、「E資格」を実務でAIを活用できるエンジニアを育成する目的で行っています。
そのため、単純な暗記問題を解けることよりも、正しい知識を正しく理解し、実践力のあるエンジニアを育てるために「認定プログラム」を用意しています。
いわば、自動車免許のための教習所のような役割だと言われています。
現在は、約十数社が「認定事業者」として登録されており、その中のどれかを選択して受講し、修了認定を受けないとE資格の受験資格が得られません。
E資格の講座の受講は時間がかかるため、仕事をしながら転職活動やE資格の講座を受講するのはなかなか大変な一面があります。
また、認定プログラムを修了すれば永続的にE資格の受験資格が得られるわけではありません。
E資格の受験資格には、「終了日試験日から遡って2年以内にJDLA認定プログラムを受講している」という条件がついているため、時間がたてば再度認定プログラムを修了する必要があります。
これは、日進月歩で新しい技術・アルゴリズムが出てくるAI・機械学習において、2年前の知識が陳腐化している可能性が大きいため、このような仕組みにされています。
JDLA認定プログラムの各社比較に関しては下記記事でも紹介しています。
E資格の受験開催日
E資格試験は、2024年現在、1年に2回のペースで開催されています。
通常、2月開催と8月開催の2回で、それぞれ試験開催年と年ごとの連番で呼ばれています。
2023年2月開催: 2023 #1
2023年8月開催: 2023 #2
2024年2月開催: 2024 #1
2024年8月開催: 2024 #2 など
過去の回では、2020 #2が、新型コロナウィルス感染予防措置のため、開催延期されており、欠番となっています。当初は1日開催の試験でしたが、2021 #1より金曜日と土曜日の2日開催、2022 #2より金、土、日曜日の3日開催となっております。
3日にはなったものの、試験自体は1日(120分)で終わるため、平日と土曜、日曜の都合の良い日程で受験することができます。
120分という試験時間のため、3日間とも受験する時間帯を選択することができます。
丸一日潰れることがないので、早めに申し込めば家庭の都合も考慮した受験ができそうですね。
E資格の申し込み可能日
E資格試験の受験申し込みは、試験日の約2ヶ月前から開始されます。
申込締切りは、受験日前日の午後11時59分までと、かなりギリギリまで申し込みができるようになっています。ですが、受験申し込みはなるべく早く済ませておくのを強くおすすめします。
E資格の申し込みに余裕を持った方が良い理由

E資格を申し込む場合は下記理由でなるべく早めに行ったほうが良いとされています。
1.試験会場の予約が必要だから
理由の1つは、試験会場の予約が必要であることです。
受験申し込みをする際に、全国の会場から自宅や職場に近い試験会場を選ぶことができるのですが、ターミナル駅の近くなど受験者数が多くなる地域では、試験会場の定員がいっぱいになってしまうことが多々あります。
新型コロナウィルス対策など定員を絞っている会場がある場合など、注意が必要です。
試験日の約1ヶ月前頃には、埋まる会場が出てくるため、できるだけ早いタイミングで予約をすることをおすすめします。
2.「修了者番号」の取得までが長いため
理由の2つ目に、認定プログラムの完了時期を考慮する必要があることです。
認定事業者は、自社のプログラムを受講して修了された方の情報をJDLAに通知し、JDLAより「修了者番号」を受け取ります。
試験の申し込み時には、この修了者番号を入力する必要がありますので、余裕を持った認定プログラムの受講と、試験申し込みをする必要があります。
3.E資格の受験資格期間は少ないから
3つ目に、E資格の受験資格期間を有効活用するためにも、早めに申し込みをすることです。
前述の受験資格により、認定プログラムを受講してからE資格を受験できるチャンスは修了者番号取得から2年間(約4回)と限られています。
万が一、1回目で不合格となった際も、再チャレンジをするために、なるべく早くから受験していただくことをおすすめします。
E資格受験の試験時間
E資格の試験時間は120分です。
試験時間は多いようにも感じますが、前回実績で104問、前々回で105問という、約100問の問題が出題され、時間内に解かなければなりません。1問に1分くらいしか時間を割けないことになるため、スピードを要求される点で難易度が高いことがわかります。
更に、設問の中には数式の計算をする必要があるものや、長めのプログラムを読まないといけない部分があるため、1問にかけられる時間はさらに短くなります。
そのため、専門用語や機械学習特有の単語などはしっかりと知識を定着させ、即答できるようにしておくことが重要です。
E資格の試験会場
試験会場は、全国に100箇所近くあり、試験申込時に近くの会場を選んで受験することができます。2024年現在、試験の運営や申込みはピアソンVUEが利用されています。
ピアソンVUEは、CBT(コンピュータ・ベースト・テスティング)と呼ばれる、コンピュータを使用した試験方式を活用したシステムで、受験申込から合否通知までの試験工程が全てインターネット上で完結するということが特徴です。
E資格に必要な受験料
E資格試験の、気になる受験料は下記の通りです。
| 受験費用(税込) | |
| 一般 | 33,000円 |
| 学生 | 22,000円 |
| JDLA会員 | 27,000円 |
学生が一番安くE資格を受験できるので、就職を控えた学生の方は今のうちに受験しておくとお得ですね。なお、不合格となってしまったときには再度受験することが可能です。
E資格を受験するメリット3選

多くの時間を使って勉強をしてE資格を取得するからには、E資格に合格していることで受けるメリットを理解しておかなければなりません。
ここでは、E資格を受験するメリットを3つご紹介します。
①社内評価や就職・転職に役立つ
E資格を持っていることは、AIに関する広く深い知識を持っているということを意味します。
そのため、社内では経営企画部やDX部、AI開発部などの最前線の職場で働くきっかけとなったり、今働いている部署内でのAI活用に向けたプロジェクトのメンバーとして活躍できる可能性が高くなります。
また、技術レベルを対外的にも示せるため、就職や転職にも役立つことになります。
E資格の合格者は、2023年末時点で、累計の合格者が7,018名であるため、資格を持っている人材は希少です。現時点で「E資格を持っていることが就職や転職をするための必須条件」としている企業は少ないかもしれませんが、今後のAIの普及により、付加価値の高い人材を現す指標としてE資格が見られるようになることが予想されます。
ですから、今後さらに就職や転職活動でもE資格は有利になるでしょう。
②AIに関する網羅的な深い知識が身につく
E資格で問われるのは、
- 応用数学
- 機械学習
- 深層学習
- 開発・運用環境
という幅広く深い知識です。AIで使用される様々なアルゴリズムの種類や、それぞれの特徴・短所を理解している必要があるため、網羅的に広く深い知識を身につけられます。
アルゴリズムの中でどのような計算がされているかを、数式を用いて理解することで、最新の論文などを読んで業務に活用する際にも役立てる事ができます。
③AI作成の実践的な知識が身につく
E資格を受ける最大のメリットはAI作成において実践的な知識が身につくことです。
E資格の受験には、認定プログラムの受講が受験条件になっています。
認定プログラムでは、AIに必要な応用数学から、機械学習や深層学習の知識の他に、Pythonを使用したプログラミングの実践的なスキルを身につけることができます。
履歴書の資格欄にE資格を記載しておけば、AIプログラミングに関しての知識があるとすぐに理解してもらえます。
④合格者コミュニティでスキルアップができる
E資格に合格すると専用コミュニティが用意されており、業界の他社AIエンジニアと情報交換すると人脈が広がり、転職など自身のキャリアアップにも役立ちます。
また、E資格の取得を通して、講座で人脈を広げることができるのも大きなメリットです。
E資格の試験問題
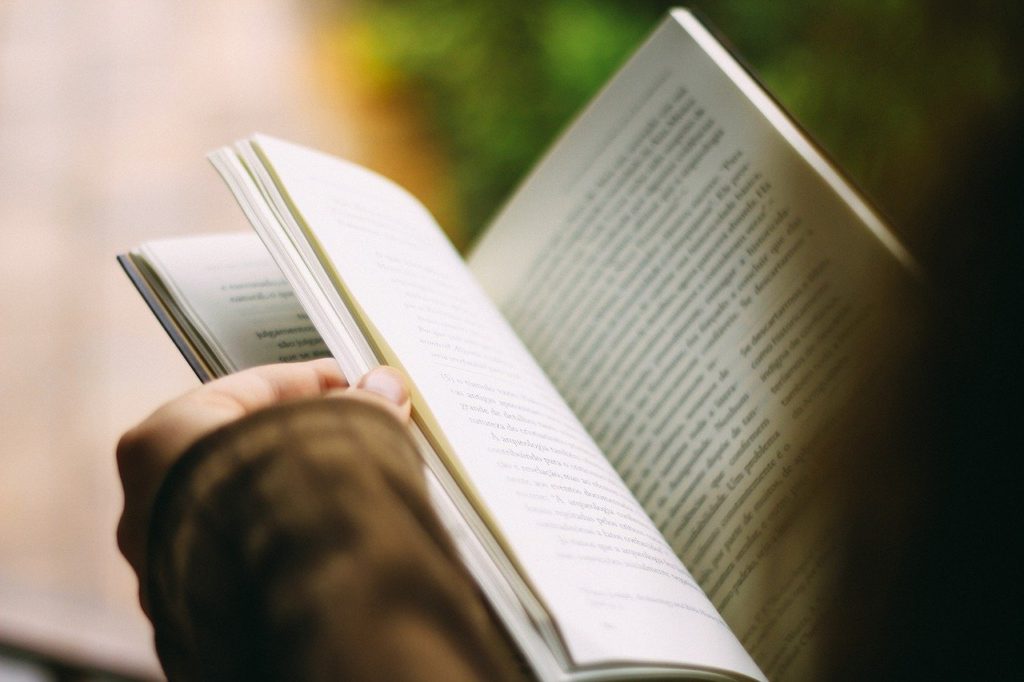
試験問題は、4択または5択程度の選択問題が出題されます。
記述問題やプログラミングをする問題は出題されません。プログラミング問題は、プログラムの一部が隠されており、少しずつ記述が異なるプログラムコードが4択で出題されるイメージです。
E資格の試験範囲は毎回シラバスが発表されているので、把握するのが比較的容易です。
応用数学、機械学習、深層学習、開発・運用環境の大項目に分かれていて、毎回少しずつ細かな内容は変更されています。
AIの分野は成長速度が速く、新しい知識の取得が求められますし、新しい問題に直面してもいます。そのため、日本ディープラーニング協会としても項目を固定するのが難しく、ディープラーニング技術の進展に伴って柔軟に変更しているのが実態です。
とはいえ、毎回のようにシラバスが変更されているわけではありません。
2024#1までは、現在公開されているシラバスが適用されることが決まっています。
シラバスは公式サイトのこちらよりダウンロードしていただけます。
シラバス変更は主に、あまり使われなくなってきたアルゴリズムを削除する、深い理論の理解を必要としていたが、実務レベルでそこまで深くの知識は不要であると判断された箇所を削除する変更が行われます。
同時に、新しく世の中で使用されているアルゴリズムについての内容を盛り込む変更も行われます。
シラバスの変更があると、今まで学んだことが無駄になってしまう、と不安に思われる方も多いかもしれません。しかしご安心ください。
新しいシラバスに則った内容に全認定プログラム事業者が講習内容の変更作業を行い、JDLAの内容チェックに合格した認定プログラムのみが提供される予定になっています。
過去の受講者への対応は各社異なる可能性はありますが、基本的には新しいシラバスに則った内容となります。また、E資格は一般に、過去問の配布も行われていません。
過去の傾向から次の試験の内容を予測するのが難しいという点でも、E資格は難しいと考えられますが、認定プログラム事業者によってはJDLAから提供される公式の例題を配布したり解説したりしているところもあります。公式の例題は、認定プログラムの受講者であっても一般に公開することは禁止されているため、手に入れるには認定プログラムを受講するしかありません。
E資格の過去問については下記記事でも紹介しています。
E資格の合格率
E資格の難易度を知る上では合格率がどの程度かが参考になります。
E資格の試験は毎年1回~2回(近年では2回)行われていますが、合格率については60~70%台を推移しています。2021年の1回目の試験については合格率が78.44%で過去最高の水準になりました。
受験者数も多く、E資格が始まってから年月も経ったので、しっかりと勉強した人の受験が目立ったと考えられるでしょう。リモートワークの推進の影響もあり、受験対策の勉強をしやすくなったのも合格率の上昇を後押ししています。
SNSなどの書き込みでは、多くの名無しIDの方からE資格の難易度が高すぎるという叫びも聞かれますが、合格率自体は70%台もあるのです。
E資格の合格基準
合格基準は公開されていませんので、何割正解すると合格になる、ということは言えないと思います。弊社にて認定プログラムを受講していただいた過去の受講者さんにアンケートを取った結果を踏まえると、60%~70%程度の正解率で合格できていそうです。
ただし、応用数学、機械学習、深層学習、開発環境などの大項目の単元ごとに正解率が出されているため、一部の単元のみ極端に低い場合などは、不合格となることもありそうです。
E資格に合格するコツ
それではそんなE資格に合格するコツは何なのでしょうか。
他の記事ではE資格に合格するコツとしてさまざまな解説をしています。
E資格のトレーニング方法を知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
また、E資格のおすすめセミナーに関してはこちらの記事で解説しています。
おすすめセミナーはJDLA認定のものばかりですので、受験資格を手に入れるためにもおすすめです。
E資格の難易度が気になる方は、E資格の難易度についてまとめた記事も参考にしてみてください。
E資格についてまとめ
今回はE資格について、試験概要や受けるメリットなどさまざまな観点から徹底解説しました。
E資格を受けようと思っている方はぜひこちらの情報を参考にしてください。
E資格の受験資格を短期間で確実に取得することができるE資格対策短期集中講座も、合わせて是非チェックしてみてください。