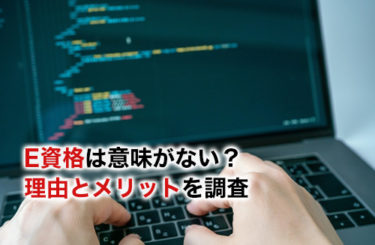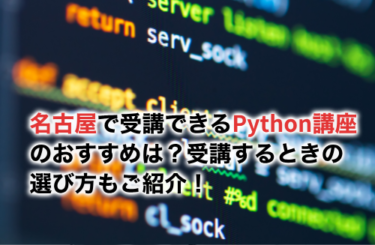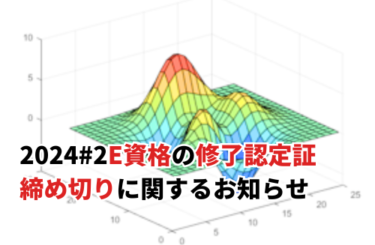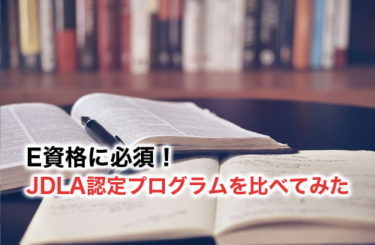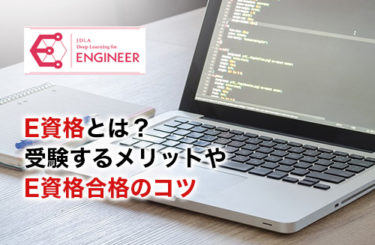最近では、最新技術であるAIの職業に就きたいと思う方が増えています。そんなAI系の就職に便利なのが「E資格」という資格・検定です。
ここでは、そんなE資格について勉強したいという方向けにおすすめの参考書を紹介していきます。
E資格とは
E資格は、JDLA(日本ディープラーニング協会)が運営しているAIやディープラーニングを理解し、実装する能力を有しているかを認定する資格です。
以下の6つを学ばなければならず、参考書を選ぶ際は6ジャンルが網羅されているものを選ぶと良いでしょう。
- 数学的基礎
- 深層学習の基礎
- 深層学習の応用
- 機械学習
- 開発・運用環境
- 実装能力
E資格の受験料
| 受験料(税込) | |
| 一般 | 33,000円 |
| 学生 | 22,000円 |
| 会員 | 27,500円 |
E資格受験の必須事項
さらに、E資格を受ける条件として、JDLAが勧める「E資格 JDLA認定プログラム」という講座を必須で受ける必要があります。
JDLAが認定した講座を必ず受けて、はじめてE資格を受検することができるようになるのです。
また、JDLAが認定する講座には教育機関以外で20前後のプログラムがあり、認定プログラム講座には、様々な内容・対象があります。
例えば、ディープラーニングについて「予め知識がある人」を対象にした講座を挙げると、〝ディープラーニングの知識がある人″というのは、〝Pythonや数学の微分などの知識を初めから知っている人″のことで、ゆえに、自分に合ったプログラム講座を探す必要があります。
E資格JDLA認定講座の前に参考書で勉強をしよう
実はディープラーニングや基本的なAIの知識がないと、講座で理解するのが困難になります。
そのため、E資格の対策は参考書でディープラーニングなどについてあらかじめ軽く勉強しておくのが大切です。
E資格は数学の微分や確率などを学ぶ必要がありますが、これらは参考書で学ぶことができます。詳しくは、後ほど解説していきますね!
E資格には、過去問問題集が一切ないので、参考書を上手く使うことが必須でE資格の合格率は60%と高く難易度も高いです。また、講座を受けるには20万円と高額なため一度講座を受けたら全てを理解する心構えが必要ですね。
そのような気持ちで講座を受けないと、よりディープラーニングの理解をますことはできないですし何より時間を無駄にしてしまいます。そのため効率よく資格を得るために、参考書でディープラーニングについてほぼ理解できる状態まで勉強し、講座を受けると、より理解が増しますよ。
E資格の受験対策についてさらに詳しく知りたい方は、E資格の難易度についてまとめた以下の記事も参考にしてみてください。
E資格の参考書の選び方
E資格を初めて受ける方は、どんな書籍から手をつけるべきかわからないですよね。
そこで、弊社がおすすめの参考書をご紹介します!
参考書は様々なものがあるのですが、今回ご紹介するのは
- 機械学習プログラミングだけを学べる本
- E資格を習得するにあたって必要な数学を学べる本
です!また参考書を選ぶコツとして、自分にあった本を選ぶのはもちろんのこと勉強の仕方なども記載している本から手をつけるといいです。
例えば、いきなりディープラーニングについて読むのは効率が悪いです。
ディープラーニングより先に知識をつけておくといいのが手法や線形モデルなど。
こういった線形モデルなどを先に学ぶことで、ディープラーニングについての知識が深まるのです。
E資格のおすすめ参考書【6選】
それでは、E資格の対策としておすすめの参考書を6つに絞って紹介していきます!
①最短コースでわかる ディープラーニングの数学
引用:Amazon
こちらの本は、ディープラーニングの本質を理解するために必要な数学を最短コースで学べる構成となっています。
ディープラーニングの理解には欠かせない数学を、高校1年生レベルからやさしく解説しているため、初めての方でも安心して取り組めます。
また、実際にコードを動かしながら学んでいくので、、ディープラーニングの動作原理を「本当に」理解できる内容となっています。
②最短コースでわかる PyTorch &深層学習プログラミング
引用:Amazon
こちらの本は、E資格から採用される「PyTorch」というフレームワークを使用し、ディープラーニングのプログラミングができるように構成されています。
機械学習の基本から、「CNN」などを使った画像認識ディープラーニングモデルの開発・チューニングまでをじっくり学べる内容となっており、プログラミングをこれから勉強してみたいという方にもオススメです。
③ゼロから作るDeep Learning③―フレームワーク編
引用:Amazon
こちらの本は、通称「ゼロつく」と呼ばれているベストセラー入門書(ゼロから作るDeep Learning)の第3弾になります。
「DeZero」という本書オリジナルのフレームワークを、全部で60のステップで完成させていく構成となっており、現代のフレームワークであるPyTorch、TensorFlow、Chainerに通じる知識を深めていきます。
④[第3版]Python機械学習プログラミング 達人データサイエンティストによる理論と実践
引用:Amazon
こちらの本は、世界各国で翻訳されている機械学習本ベストセラーの第3版になります。
分類/回帰問題~深層学習/強化学習まで、機械学習コンセプト全般をカバーしており、理論的背景とPythonコーディングの実際を解説しています。
著者の経験に基づく洞察と、より専門的な知識を学ぶことができる構成となっており、理論と実践を架橋する解説書の決定版です。
⑤scikit-learn、Keras、TensorFlowによる実践機械学習 第2版
引用:Amazon
こちらの本は、E資格から採用される「TensorFlow」などのフレームワークを使用し、機械学習で問題を解決に導くまでの一連の手法を体系立てて解説しています。
問題に対してサンプルデータを示しつつ、コードを動かしながら機械学習が使えるようになることを目的としています。アルゴリズムの説明に留まらず、実務で必要となるスキルをまとめた本書は、機械学習を学びたいエンジニア必携の一冊です。
⑥深層学習 改訂第2版 (機械学習プロフェッショナルシリーズ)
引用:Amazon
こちらの本は、ベストセラーである深層学習 (機械学習プロフェッショナルシリーズ)(2015/4)の改訂版になります。
深層学習における「なぜうまく働くのか」「なぜそうすべきか」といったさまざまな課題に対して、筆者が実務家を通して考察してきた、現時点で最も納得できるような道しるべを示してくれています。深層学習の実用的な内容も含まれているため、網羅的な理解にも役立ちます。
ディープラーニングを業務で利用している、あるいはこれから利用しようとしている人にもオススメです。
これまでおすすめの参考書を紹介してきましたが、他のサイトでもE資格の参考書について説明されているので、チェックしてみてください!
E資格の参考書にプラスすべき問題集・例題
これまでご紹介してきた参考書を使用しつつ試験範囲をある程度インプットしたら、次のステップとして問題集を解いたり、模擬試験を受けるなどのアウトプットの機会を設けられると良いでしょう。
E資格の合格率は、例年70%前後と決して低くはありません。
G検定のように誰でも受けられる試験ではなく、JDLA認定プログラムの修了が受験資格として設けられています。
また、受験料も高額なので、できるなら一発で合格したいものです。
そのためにも、問題形式や時間配分などを掴んでおくことが必要です。
そこで、現在でも唯一であるE資格向けの問題集をご紹介します!
E資格の問題集
徹底攻略ディープラーニングE資格エンジニア問題集 第2版
上記でも触れましたが、こちらはE資格向けとしては唯一と言っていい問題集です。
引用:Amazon
2021年5月に新しく第2版として改訂され、前回よりも内容が精査されています。
過去にE資格を優秀な成績で合格した人が執筆しており、網羅性も完璧で、問題に対する解答がとても詳しいので、理解も深まります。すでにディープラーニングや機械学習を実務で使っているAIエンジニアが自分のレベルを確認するのにも役立ちます。
実際の試験と同じく多肢選択式の問題を掲載しているので、試験自体にも慣れることができます。JDLA認定プログラムの講座の受講と合わせて解いていきたい1冊です!
E資格の例題
さらにE資格の問題例を解いて学習したい方には例題を提供している学習サイト「ProSkilll」もおすすめです。ProSkilllでは問題例が23問用意されていますので、一度腕試しに挑戦してみてもいいでしょう。
参考書より分かりやすいE資格講座
E資格を確実に取得するためには、参考書を読み込むなどの対策が必須です。
さらに講座も受講しておけばより理解度が深まり、合格に近づきやすくなることでしょう。
おすすめのE資格講座を紹介します。
おすすめの講座「E資格対策ディープラーニング短期集中講座」
E資格の合格を目指す方におすすめのE資格講座は、E資格対策ディープラーニング短期集中講座です。
こちらの講座では、最初にオンライン学習を受講して、基本知識を学びます。
事前学習の時間は、全8.5時間です。
最初の段階で、ディープラーニングやPythonのプログラミングや応用数学などの基本をしっかりと学びますので、無理なく次のステップに進むことができるでしょう。
事前学習を終了した後は、計4日間のセミナーを受講するという流れです。
| 学習内容 | |
| 1日目 | 機械学習アルゴリズムの仕組み |
| 2日目 | バッチアルゴリズム、ミニバッチアルゴリズム、隠れユニットや出力ユニットの活性化関数など ニューラルネットワークを実装できるレベルを目指す |
| 3日目 | 畳み込みニューラルネットワーク 画像認識アーキテクチャの実装に欠かせないスキルを身に着ける |
| 4日目 | 回帰結合型のニューラルネットワーク、自然言語処理、双方向RNNなど |
受講方法は、会場受講、ライブウェビナー、eラーニングの3つの形態から選択可能です。
どの受講形態も、フォロー体制が用意されていますので安心です。
なお、受講者はE資格完全攻略テキストブックや暗記用のテキスト資料などがもらえます。
参考書と合わせて試験対策に活用してみるとよいでしょう。
その他のE資格講座を比較したい方は下記サイトも参考にしてください。
E資格に合格するメリット
E資格を習得することで、ディープラーニングを実装している会社に就職しやすくなるのは間違いないです。
日本ディープラーニング協会(JDLA)が推奨しているように、E資格を持っている人は昨今不足しています。簡単ではないですが、AI資格を持っておくだけでも就職活動に非常に役に立ちます。
またディープラーニングというのは、「大量のデータを使うことでコンピューターが学習し、人間の力なしに動く」ことを指します。つまりそのディープラーニングを自動車に実装することで、自動運転になるということですね。
最近では、そういった技術が注目されているので、ぜひE資格を手にしてくださいね。
E資格のおすすめ参考書についてまとめ
今回は先に講座を受けてから参考書で学ぶのか、それとも参考書で学んでから講座を受けるべきかをご紹介しました。
おすすめなやり方が、はじめに参考書で学び、そのあとにディープラーニング協会が認定している講座を受ける方法です!AIの資格を手に入れるのはかなり大変ですが、E資格を持っていると企業からも重宝されるので頑張ってくださいね!
先述したように、AI研究所が開催しているE資格対策ディープラーニング短期集中講座は、日本ディープラーニング協会にて規定されている出題範囲をすべてカバーしているセミナーです。
セミナーの内容は常に最新のE資格に完全対応しています。
試験対策を中心に、E資格に合格するためのポイントを絞って学習できます。
誰にでも理解できるように、わかりやすく丁寧に教えてもらえるため、専門用語などがわからない方でも全く心配はありません。この機会に是非、受講されてみてはいかがでしょうか。

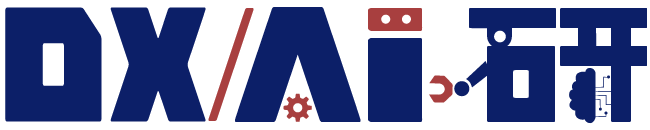

 引用:
引用: 引用:
引用: 引用:
引用:![[第3版]Python機械学習プログラミング 達人データサイエンティストによる理論と実践](https://m.media-amazon.com/images/I/81dC32FEpGL._SL1500_.jpg) 引用:
引用: 引用:
引用: 引用:
引用: 引用:
引用: