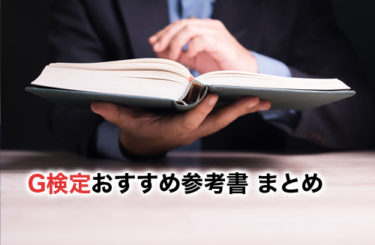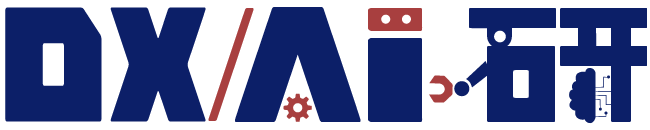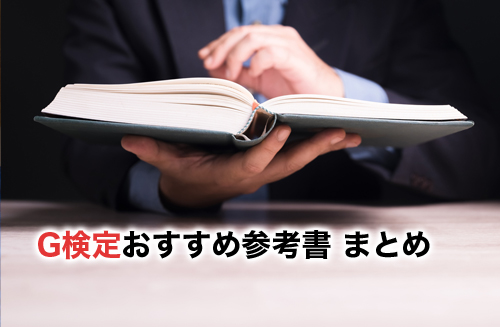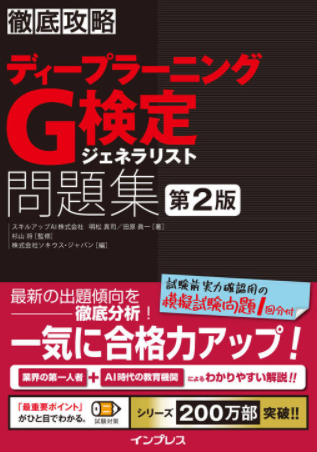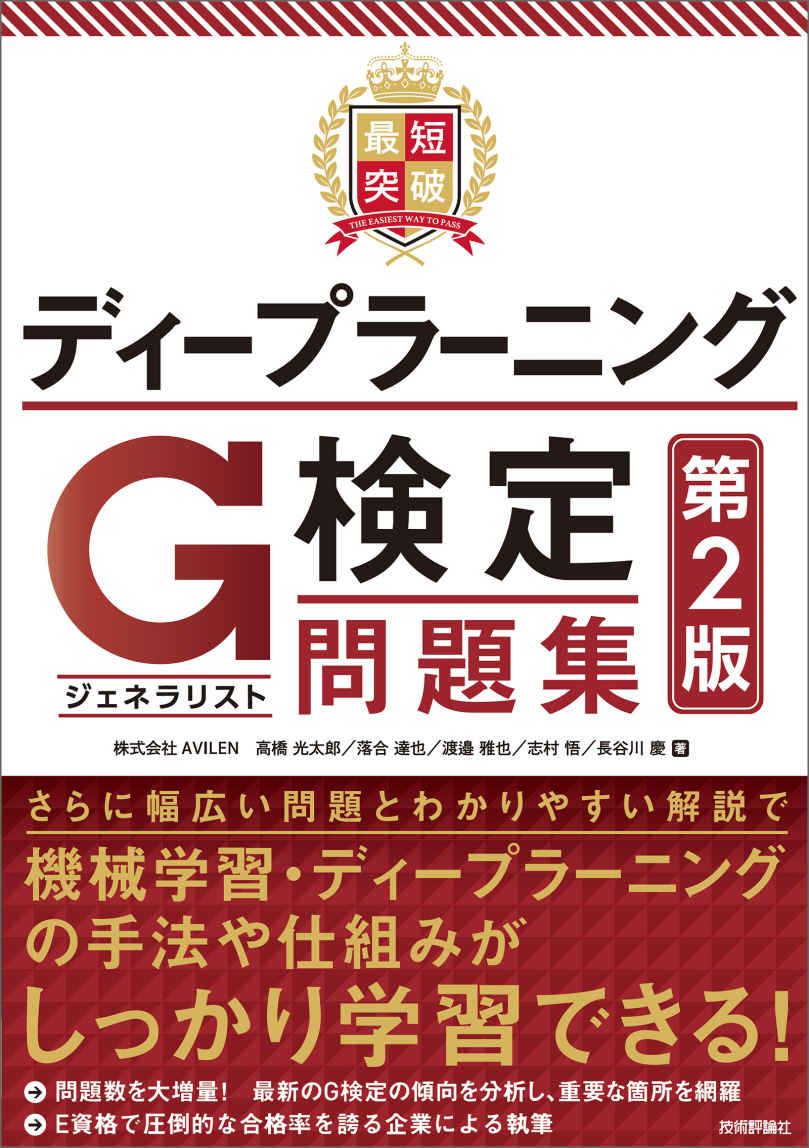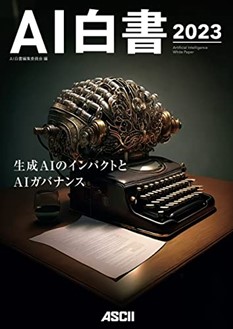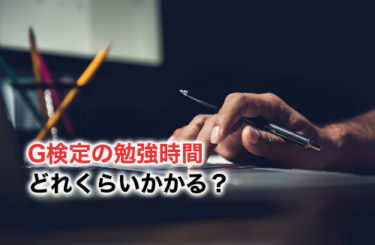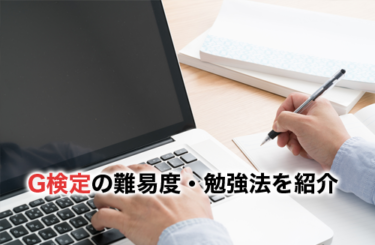G検定はAIを学ぶ上での登竜門的な位置付けであり、直近の受験者数も大きく伸びている人気の資格です。
しかし、その難易度は決して低くありません。後ほど詳しく解説しますが、いわゆる「公式テキスト」だけではカバー率が低く、+αの学習が重要になってきます。
参考書の紹介と合わせて、具体的な活用方法や学習法についてもお伝えしています。G検定取得を目指す方のご参考になれば幸いです。
G検定とは

G検定とは、一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が実施する、AI・ディープラーニングの基礎知識を問う試験です。試験に合格することで、AIの基礎知識、機械学習、ディープラーニング、数理・統計などの知識を有していることを証明できます。
ビジネスパーソンにとって、AI活用の第一歩としてG検定の取得はおすすめです。
G検定についてはこちらの記事でも解説しています。
G検定のおすすめ参考書
それではG検定合格にむけておすすめの参考書をご紹介します。
G検定のおすすめ参考書1.ディープラーニング G検定公式テキスト
引用:Amazon
まずはじめに紹介するのが、日本ディープラーニング協会監修の公式テキストです。通称「白本」と呼ばれており、G検定の受験者の大半はこのテキストを使用して学習を進めるものと思われます。
AIの基礎を体系的に学びつつ、章末の練習問題で随時理解度をチェックしながら学習を進めていきましょう。人にもよりますが、最低でも2周、時間に余裕のある方は3周以上読み込むのをお勧めします。
G検定受験者が全幅の信頼を置く、この「白本」ですが、注意点が2点あります。
注意点①公式テキストの試験内容カバー率について
注意点の1つ目は、試験内容の「カバー率」です。
冒頭でもお伝えしましたが、実際にG検定を受験した人の声を聞いてみると、この白本だけでは試験全体の3~4割程度しかカバーできていないと言われています。
基礎的な内容で分かりやすく作られている良書ですが、あくまで「基礎」だという認識を持っておかないといけませんね。
注意点②第3版について
注意点の2つ目ですが、この「白本」は2024年5月に第3版が出版されました。新たに購入される方は、この新しい「第3版」で学習を進めましょう。
AIの分野において日々の情報のアップデートや技術の進歩は、ものすごいスピードで行われています。G検定はそのAIという領域の性質上、試験内容も常に最新の情報にアップデートされています。
白本に限ったことではありませんが、古い参考書の情報では最新情報を問われる問題に対応できないケースがあります。中古等で購入を検討している方は、要注意です。
G検定のおすすめ問題集
最近ではG検定対策の問題集が増えていますが、ここでは2つに絞って紹介していきます。いずれも、G検定公式HPに記載のある「G検定合格者のおすすめ書籍」に選ばれています。
G検定のおすすめ問題集1.徹底攻略ディープラーニングG検定ジェネラリスト問題集 第2版
引用:Amazon
こちらは通称「黒本」と呼ばれており、白本と合わせて人気の参考書です。白本との内容の親和性も高く、解説も丁寧で分かりやすい、「まずは白本と黒本」という位置づけの一冊です。
一方で、白本と同じく内容が基礎的であり、試験内容のカバー率自体は高くないとも言われています。白本+黒本+αが必要ではないかとされていましたが、2021年6月に、黒本「第2版」が出版され、これまで黒本の弱点とされていた「AI関連の法律、契約」の分野が追加され、グッとカバー率は上がったのではないでしょうか。
2021年春に発表になったG検定出題範囲の新シラバスに対応している、数少ない問題集となっています。
G検定のおすすめ問題集2.最短突破 ディープラーニングG検定(ジェネラリスト) 問題集 第2版
引用:Amazon
こちらは通称「赤本」と呼ばれている問題集です。2022年8月に、待望の赤本「第2版」が出版されました。
従来の黒本よりもカバー範囲が広く、新しい分野にも対応していると言われていました。特にディープラーニングの領域のカバー率が高く、深層強化学習などの新しい分野をカバーできているのは赤本独自の強みでしょう。
他の問題集と比べ、解説がとても詳細まで記載されており、問題集ではなくテキストのような使い方も可能です。白本や黒本で基礎を固めた後に集中して取り組むのが良いでしょう。
G検定のおすすめ書籍

G検定の学習には参考書や問題集の他にもおすすめの書籍があります。
G検定のおすすめ書籍1.AI白書 2023
引用:Amazon
この本はAIの最新技術や新しい社会情勢、法律や政策などが書かれている書籍です。G検定の参考書として出版されている書籍ではなく、AIの最新の取り組みや動向を掲載することで、企業のAI導入を推進する目的の書籍とされています。
少し話が逸れますが、G検定で最も難しいと言われている分野の一つに、
- 最新の政策
- 法律
- 時事問題
などが挙げられます。問題数としてはディープラーニング関連が最も多いですが、一方で最新の政策や法律、時事問題などの領域は非常に対策が難しいです。
そもそも、どうやって学習したらいいか分からない人も多いのではないでしょうか。web上のAI関連の記事、ニュースを検索したり、Youtubeで動画を見漁ったりと、これといった学習方法が確立していないのです。
そのような対策困難な分野をカバーしている書籍が、このAI白書です。盤石な状態でG検定試験を迎えたい方にはオススメの一冊です。
注意点①内容が体系化、実際の問題での出題量について
参考書ではないため、内容が体系化されてまとまっているわけではありません。また、本書の内容で実際に試験に出題される量は多くないかもしれません。G検定対策の参考書ではないので致し方ない部分ではあると思います。
さらに、内容自体も難しいものが多く、基礎知識が無いと理解に時間がかかってしまうでしょう。
書籍で学習する以外にも、AIについて学べる講習を受講することもおすすめです。以下の記事ではおすすめのAI講習を紹介しています。
注意点②
2021年7月時点での最新版が2020年3月に出版されたものですが、もしかすると最新版が出るのを待ったほうが良いかもしれません。しかし、G検定対策で本書を購入するメリットは「AI業界の最新の動向や時事問題に触れることができる」ことでしょうから、どうせならより新しいAI白書を手に取りたいでよね。ちなみに、出版社からの改訂の案内はありませんので、最新版がいつ出版されるのかは現時点で分かりません。
※2023年5月に最新版の第5巻が発売されました。
参考書でカバーできないことって?

ここまでG検定の参考書についてまとめてきました。しかし、G検定の試験の性質上、参考書だけでは対策不十分な点がどうしても出てきます。
- 模擬試験
- 最新動向
参考書でカバーできないこと①模擬試験
G検定は、自宅のオンライン環境で受験します。試験時間120分で200問と、時間にシビアな試験である一方で、試験中のGoogle検索や書籍の参照が認められています。
この試験の形式に慣れておかないといけないため、Webで、G検定本番形式の模擬試験を受験しておく必要があると思います。
参考書でカバーできないこと②最新動向
ここまで何度もお伝えしておりますが、AI業界の性質上、G検定では最新の取り組みや動向についての問題が多く出題されます。
参考書では情報のアップデートがされていないケースもあり得るため、タイムリーに教材を最新状態にアップデートできるオンライン講習なども有用です。
AI研究所でも、G検定対策講座を開催しております。ご興味のある方は一度のぞいてみてはいかがでしょうか。
G検定の参考書についてまとめ
G検定のおすすめの参考書とその特徴についてまとめましたが、いかがだったでしょうか。自分に合う参考書が見つかったら早速G検定の勉強を開始しましょう。