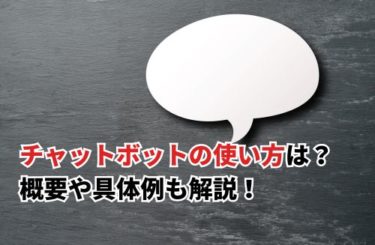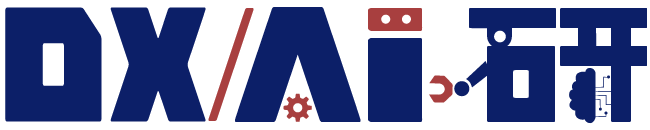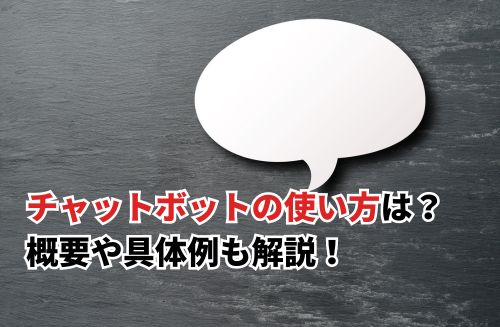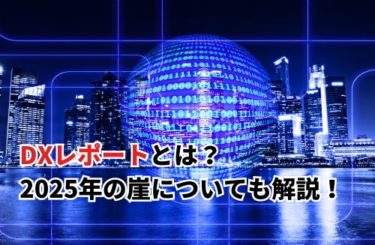コールセンターをはじめWebサイトや観光案内など、各業界で幅広く活用されている「チャットボット」。導入のメリットや輝かしい成功例を見て「弊社でも導入したい」と考える方は多いのではないでしょうか。
新しくビジネスに導入するなら、できることや使い方をイメージしておくことが大切です。今回の記事ではチャットボットの概要や種類、実現できること、使い方や導入成功事例を紹介します。
本記事を読むことで種類や使い方がわかり導入成功イメージの明確化につながるので、参考にしていただければと思います。
そもそもチャットボットとは?
簡単にいうと「AIと会話ができるプログラム」です。ユーザーが音声およびテキストで質問をすると、それに沿った回答を行ってくれることから、さまざまなシーンで活用されています。
身近な例で例えるとiPhoneに搭載されている「Siri」や各種スマートスピーカー、2023年に話題となった「ChatGPT」などが挙げられます。ちなみに直訳するとチャットは「会話」で、ボットは「ロボット」という意味です。
チャットボットの種類は主に3つ

大きく以下の3つに分類されます。
| 種類 | 特徴 |
| シナリオ型チャットボット | 選択式の質問で、シナリオどおりの答えを返す |
| 辞書型チャットボット | 単語の入力のみで、適切な提案や回答を生成する |
| AIチャットボット | AIが会話から自動学習し、回答の精度を上げていく |
それぞれ、順を追ってご紹介します。
シナリオ型チャットボット
その名のとおり、シナリオに沿った回答を生成してくれることからこのような名称で呼ばれています。さらにシナリオ型チャットボットは、以下のように細かく分類されます。
| 分類 | 特徴 |
| 選択肢型 | 選択式またはイエス・ノーで答える方式 |
| ログ型 | 会話データの学習によって徐々に精度を上げていく方式 |
比較的リーズナブルな金額で開発・納品が可能な一方、シナリオにない質問への回答ができない点がデメリット。この背景から「人工無能」と呼ばれることもあります。
辞書型チャットボット
単語を入力するだけで、質問にマッチする答えを生成してくれるタイプです。たとえば「配達状況」と入力するだけで、伝票番号の入力を求めるフォームを返してくれるといった具合です。
前述のシナリオ型とは違って自由な形式で質問ができたり、安価でスピーディーな開発が可能な点がメリットです。しかし、登録されていない単語に対する回答はできないことがデメリットといえます。
AIチャットボット
AIが会話データから学習および改善を行って、質問に対し高度な回答を生成する形式です。開発者があらかじめ学習させるデータはもちろん、実際のユーザーとの会話内容をデータとして自動で学習するため、使っていくごとに賢くなっていく点が大きな特徴になります。
長期的に学習やメンテナンスを行うことであらゆるシーンで活躍するシステムに育つものの、開発に大きな時間とお金が必要になること、また学習が未熟なうちは的外れない回答や誤情報を提示してしまうことはデメリットです。
チャットボットで実現できること
できることはじつにさまざまですが、代表的なものを挙げると以下のとおりです。
- 問い合わせ数の削減
- 問い合わせ対応の自動化
- サービスの質や顧客満足度の向上
それぞれ見ていきましょう。
問い合わせ数の削減
問い合わせ数の「削減」は、チャットボットで実現できることの代表例として挙げられます。ユーザーがよく行う質問は、チャットボットが解決してくれるからです。
これまではどんな質問にもメールや電話で対応することが一般的でしたが、簡単な質問や回答が決まりきっている質問を回答させることで、人間が電話やメールで対応する件数を圧倒的に削減できます。
問い合わせ対応の自動化
チャットボットは24時間365日の対応が可能なことから、問い合わせの完全自動化が実現します。よく寄せられる質問やイエス・ノーで答えられる簡単な問い合わせであれば、大きな問題もなく対応できるでしょう。
従来であれば電話やメールによる膨大な問い合わせに対応すべく大量の人材を雇う必要があり、大きなコールセンターの設置や人件費にもお金がかかっていましたが、その費用も大幅に削減可能になります。
サービスの質や顧客満足度の向上
チャットボットの活用は、サービスの質や顧客満足度の向上にもつなげられます。ユーザーが選択した質問や問い合わせた内容などをデータとして蓄積させ、それらを分析することでより効果的なマーケティング戦略が立てられるからです。
たとえば「荷物の集荷を依頼するときの方法」に関する質問がよく寄せられるなら、トップページの集荷依頼のボタンをより際立たせるなど、適切な対策が可能になります。またその他の質問や意見を参考にすることで、ユーザーニーズに合わせたよりよいアップデートを行えるようになるでしょう。
入力内容は「ユーザーのありのままの意見」そのものなので、改善にあたって大きな価値を発揮します。
チャットボットの使い方

ここでは「チャットボットがどのような使い方がされているのか」について、以下の5つの例をご紹介します。
- コールセンターおよび社内ヘルプデスク
- 観光案内や施設案内
- WebページおよびECサイト
- 職員採用面接
- 各自治体による行政案内
コールセンターおよび社内ヘルプデスク
コールセンターや社内ヘルプデスクでは、チャットボット活用によって多くの問い合わせを自動化することでオペレーターの負担軽減に役立っています。24時間いつでも問い合わせが可能になることでオペレーターの負担が軽減されるだけでなく、ユーザー側にも「営業時間になるまで待つ必要がない」というメリットがあります。
また社内ヘルプデスクでも、チャットボットが従業員の自己解決をサポートすることで担当者の負担が軽減するほか、組織全体の生産性と効率性向上にも役立っています。
観光案内や施設案内
観光案内にて観光地情報や周辺スポット、施設の営業時間や料金、アクセス方法などを素早く提供する用途でも用いられています。
また施設案内では展示物や設備の説明、施設内の案内などをチャットボット化することで、従業員の業務負担を軽減しつつ観光客や利用者のサポートを行うことに成功しています。
さらに新型コロナウイルスを皮切りに、受付窓口を非接触・非対面形式に変更する企業も増えました。
WebページおよびECサイト
WebページやECサイトでもさまざまな使い方が実現しています。ページの特定の箇所に設置されている会話式チャットボットが代表例です。
会話式チャットボットは製品やサービスに関する情報提供や購買支援、注文の受付や配送状況の確認などにも返答が可能です。この他にもチャットボットで自由なコミュニケーションを経て、ユーザーの興味を惹きそうな商品の提案を行ってくれるものなども存在します。
職員採用面接
各企業や自治体に置ける採用面接にも応用されています。
たとえば応募者との最初のコンタクトポイントとしてチャットボットを導入し、応募者の基本情報や志望動機などを収集。面接のスケジューリングや面接前の質問事項に対する回答、そして会社や職種に関する情報提供も行います。
最終的には人間による面接が必要にはなるものの、採用担当者の負担を大きく軽減していることは言うまでもありません。
各自治体による行政案内
企業のみならず、行政案内の用途でも使われています。たとえば厚生労働省は新型コロナウイルスの影響から、ワクチンに関する問い合わせ窓口としてシナリオ型チャットボットを活用したLINEの接種予約システムの提供を始めました。
それだけでなく国内のさまざまな市区町村でも、公式サイトに設置することで各種手続きや観光案内、イベント情報などの自動提供を実現しています。
チャットボット導入に成功した具体例

ここではチャットボット導入に成功した具体例として、以下の3つの企業をご紹介します。
- 株式会社サンベンド
- 花キューピット株式会社
- rinna株式会社
株式会社サンベンド
サントリーのグループ会社「サンベンド」は、サントリー系自販機を全国に数十万台展開しています。提供する自販機の数が多いこともあり、コールセンターの人手が問い合わせ件数に対して圧倒的に不足していること課題でした。
そこでサンベンドは「Kore.ai Virtual Assistant Platform」を採用し、これまでに例のない自販機コールセンターのAIチャットボット窓口を開設。人間によるコールセンター業務の40%削減を目標に、着実に運用を行っています。
花キューピット株式会社
近所の花屋さんからの直接配送サービスを行う花キューピット株式会社は、カスタマーセンターの人材や場所の確保、さらに繁忙期の膨大な件数の問い合わせへの対応が困難といった課題がありました。
そこでチャットボット「さっとFAQ」を導入しよくある簡単な問い合わせを自動化することで、職員の負担と人件費を削減することに成功しています。
rinna株式会社
こちらは生産性向上や業務効率化ではなく、娯楽・エンタメとしてのチャットボット成功事例となります。
rinna株式会社が提供する女子高生AI「りんな」は、ユーザーの質問に対する正確な回答というより「共感」を呼ぶフランクな話し言葉を返してくれるチャットボットです。思わず会話を続けたくなる仕組みから、若年層を中心に話題と人気を集めました。
架空のキャラクター「りんな」は現在、チャットボットの域を超えアーティストやYouTuberなど、活動の幅を広げています。
チャットボットを学ぶなら「チャットボット入門セミナー」!

AI研究所が提供する「チャットボット入門セミナー」は、AI学習の完全未経験者でも実務で使える応用レベルのチャットボット知識を1日で習得できるセミナーです。
仕組みや種類といった基礎から実装方法といった応用まで、実際にチャットボットを作りながらハンズオンで学習できるため、スムーズな理解が可能となっています。
また「コスパ重視の方が選ぶAIセミナー」で第一位を獲得した実績があり、35,200円と他のセミナーと比較してもリーズナブル。満足度も97.8%と高水準です。
最速でAIチャットボットの作り方および活用法を学びたい方は、ぜひご検討ください。
まとめ
チャットボットの使い道はコールセンターをはじめとする問い合わせ業務の他にも多種多様で、さまざまな業界で役立てられています。
とはいえ、もちろんチャットボットでは実現できないこともたくさんあります。導入の際は「チャットボット導入で自社でどういう目的を達成したいのか」を明確にしたうえで、実現できることの範囲内で運用していくことが大切です。
AI研究所の「チャットボット入門セミナー」なら満足度97.8%のセミナーで初心者でも安心して効率よく、そしてリーズナブルにチャットボットを学べるのでぜひご検討ください。