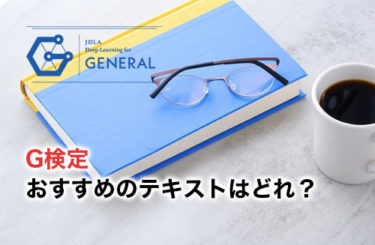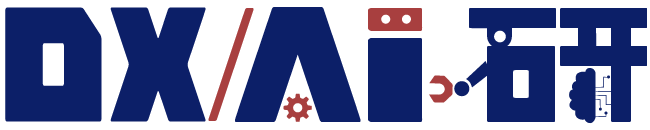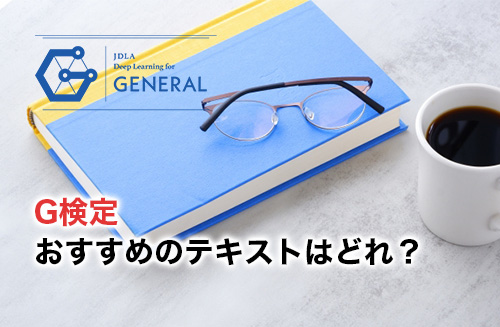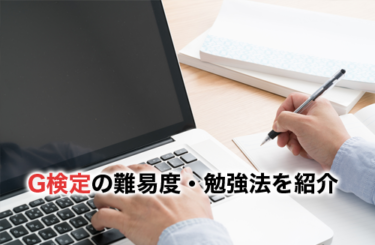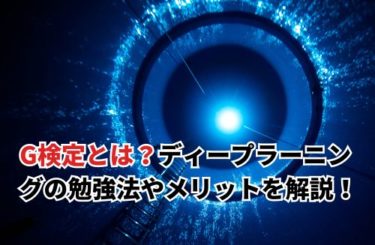AIやディープラーニングの需要拡大から、AI資格「G検定」に興味をもつ方は増えています。それに伴ってG検定のテキストも年々種類が増えており、どれを選べばいいか悩む方は多いのではないでしょうか。
今回の記事では、G検定のおすすめテキストをはじめ、選び方や活用方法など合格につながる有益な情報をご紹介します。これからG検定に挑む方は、ぜひ参考にしてください。
G検定の概要

G検定は、「一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)」が運営する資格の一種。AIおよびディープラーニング、データ解析などに関する高度な知識をもつことを証明するものです。
単にAIに関する知識をつけるだけでなく、ビジネスに活用するための応用力も求められるジェネラリスト向けの資格となっています。その他、G検定の詳しい概要は以下をご覧ください。
| G検定の目的 | ・AIやディープラーニングなどに関する高度な知識の証明 ・上記をビジネスに活用する応用力の証明 |
| 資格の正式名称 | G検定 |
| 運営機関 | 一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA) |
| 試験日時 | 年3回(3・7・11月) |
| 受験に必要な資格 | なし |
| 費用(税込) | 一般 13,200円 学生 5,500円 (2年以内の再試験の場合) 一般 6,600円 学生 2,750円 |
| 会場 | 自宅(オンライン受験) |
| 試験時間 | 120分 |
| 主な出題内容 | ・人工知能(AI)の概略 ・近年の人工知能のトレンド ・ディープラーニングの概略 ・ディープラーニング手法の具体例 ・データ分析や統計学 |
G検定の合格のためにかかる勉強時間
G検定の合格のために必要となる勉強時間は、おおよそ30~40時間となっています。まったくの未経験からAIを学習する方で約40時間、実務でAIに触れている方などで約30時間と考えていいでしょう。
ただ勉強時間はあくまで目安であり、各々の学習方法や効率などで大きく変動するものです。G検定の効率のいい学習法については、以下の動画も参考になります。
G検定に合格するためのおすすめテキスト5冊
ここからは、G検定の合格に役立つおすすめテキストを5冊に絞って紹介します。
深層学習教科書 ディープラーニング G検定(ジェネラリスト)公式テキスト

引用:Amazon
こちらはG検定の運営元である日本ディープラーニング協会(JDLA)が執筆・監修を手がけた、G検定テキストのベストセラーです。公式テキストであることから最新の問題動向にも対応しており、一冊で必要十分な知識を学べます。
G検定の合格を目指す方はもちろん、新しくAIに触れる方、AIやディープラーニングを業務で有効活用したい方に最適です。
ディープラーニングG検定(ジェネラリスト)最強の合格テキスト
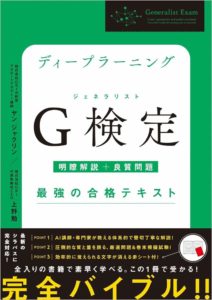
引用:Amazon
AI講師および専門家による監修のもと、親切丁寧な解説を体系的に学ぶことができるテキストです。良質な問題と設問数を誇るテキストとして評判が高く、「わかりやすさ」にこだわって制作されています。
また試験対策として有益な半透明の赤シートがついているので、効果的なアウトプットを期待できます。
これ1冊で最短合格 ディープラーニングG検定ジェネラリスト要点整理テキスト&問題集
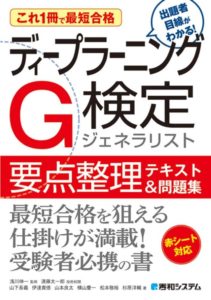
引用:Amazon
「最短で合格できるようになること」に注力して執筆されたこちらのテキスト。よく出題される設問が厳選してまとめられ、さらに簡素なレイアウトでわかりやすく制作されています。
数式よりも文章、文章よりも図や表を効果的に活用しているため、スムーズにインプットができるでしょう。効率的にG検定の重点を勉強したい方におすすめです。
スッキリわかる ディープラーニングG検定(ジェネラリスト) テキスト&問題演習

引用:Amazon
こちらは過去のG検定の出題傾向から、よく出る部分のみを効率的に学習できるテキスト。各分野やパートごとに「最重要項目」が設けられている点がポイントです。
付属の予想問題集の質も高く、バランスのとれたインプットおよびアウトプットを行うことができるでしょう。ゼロから体系的に学ぶよりも、重点を徹底的に知りたい方におすすめです。
この1冊で合格! ディープラーニングG検定集中テキスト&問題集
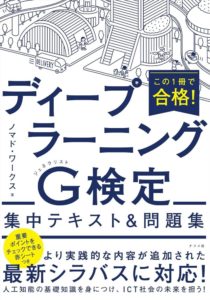
引用:Amazon
他のG検定対策テキストと比較しても、より実践的な内容を学べる一冊です。たとえば出題テーマの中の理解すべき点を図解や表で解説したり、分野ごとにマルバツチェックなどが設けられています。
もちろん最新のシラバスに対応しているため、安心して学習に取り組めるでしょう。最終章には模擬試験も掲載されているため、効率よりも堅実に実力を付けたい方におすすめです。
G検定のテキストの選び方
G検定のテキストを選ぶ際は、以下のポイントに着目することが大切になります。
- G検定公認の公式テキストを選ぶ
- 解説のわかりやすさをチェックする
- なるべく発刊日が新しいものを選ぶ
この章では「G検定テキストの選び方」として、上記それぞれを詳しく解説します。
G検定公認の公式テキストを選ぶ
テキスト選びにおいて、G検定が公認しているものを選ぶことは大切です。やはりG検定が公認で監修や執筆を行っているものは、信頼性や権威性が高いためです。
信頼性や権威性が高いということは、傾向としてテキストの内容がそのまま試験に出る可能性が高いということでもあります。テキスト選びに迷っているなら、G検定公式のテキストを選んでおけば、大きな失敗は防げるでしょう。
解説のわかりやすさをチェックする
解説のわかりやすさは、テキスト選びにおいてとくに重要なポイントになります。いくら問題数や情報量が充実していても、解説が分かりにくければ、挫折率が大きく上がってしまうためです。
G検定においては、紙のテキストを用いた勉強法だと、挫折率が高い傾向にあります。購入前に現物を手に取り、ひととおりページをめくってみて、「自分に合っていそうか」「理解できそうか」を確認するのがベストです。
なるべく発刊日が新しいものを選ぶ
G検定のテキストは、なるべく発刊日が新しいものを選ぶようにしましょう。G検定の根幹となるAIやディープラーニングは、進化や流行り廃りが激しい分野だからです。
AIの進化やトレンドはもちろんですが、G検定の出題傾向も変わる可能性はあります。なのでテキストは、古くてもせいぜい2~3年前のものに留めるようにしましょう。
G検定に受かるためのテキスト活用方法

G検定に受かるためには、テキストをいかに有効活用するかが成否を分けます。
G検定のテキストを有効活用するコツとしては、次のとおりです。
- インプットよりもアウトプット中心で学ぶ
- 苦手な部分ばかりの学習に気をつける
- 問題集と併用する
上記それぞれ順を追って解説します。
インプットよりもアウトプット中心で学ぶ
テキストを用いた学習では、インプットよりもアウトプットを中心に行うほうが効率がいいです。アウトプットを行わないと、知識を脳に定着させることができないためです。
「テキストをひたすらに読んで、余裕の状態になってから模擬試験に挑む」という方は少なくありませんが、あまり効率がいいとは言えません。テキストはざっと読んだら、あとは模擬試験に時間を割くべきです。
アウトプットを行うことで、はじめて苦手な部分および解けない理由がわかってきます。インプット3割、アウトプット7割を意識しましょう。
苦手な部分ばかりの学習に気をつける
はじめてG検定に挑む方や、資格の勉強に慣れていない方は、学習の偏りが生まれがちです。とくに多いのが「苦手な部分ばかりを勉強してしまう」という方。
苦手な部分の克服にある程度時間をかけることは有益です。しかしそれに満足し、他の部分をないがしろにしてしまっては、本末転倒です。
G検定は範囲が広いので、広く浅くコツコツ学習するほうが効果的といえます。
問題集と併用する
G検定のテキストは、問題集と併用して使うことで、より学習効率は上がります。近年で販売しているG検定のテキストは問題集もついていますが、やはり設問の数は専門の問題集には及びません。
問題集を用いてアウトプットをしつつ、解けなかった部分をテキストでインプットしていくのが、G検定における効率のいい勉強法です。
G検定のテキスト以外の学習方法

テキストを用いたG検定対策は、なかなか難しく続かないという方も多いでしょう。そのような方におすすめの、テキスト以外のG検定学習方法には、次のようなものがあります。
- インターネットの情報や教材
- プログラミングスクール
それぞれ解説します。
インターネットの情報や教材
インターネットの情報や教材を用いて、G検定対策を行う方法です。Ai需要の高騰からG検定の人気も高まっているため、インターネット上にはG検定のあらゆるノウハウが溢れています。
またG検定においてはわかりやすい有料の動画教材なども販売されているので、積極的に活用するといいでしょう。有料の講座については次の記事も参考になるので、ぜひご覧ください。
プログラミングスクール
G検定テキストでの独学が続かない方におすすめなのが、プログラミングスクールの活用です。現代ではあらゆるプログラミングスクールが、G検定対策コースを設けています。
G検定の出題範囲には、Pythonを用いたプログラミングも含まれます。PythonおよびAIプログラミングから始めてみるのも、G検定対策として有益です。
AI関連のプログラミングスクールなら、以下の記事もぜひ参考にしてください。
さらに合格率アップを狙うならProskillを活用しよう!
テキストやネットでの学習に加えて、さらに合格率を上げたいなら、Proskillが運営する「JDLA認定 G検定対策講座」を活用してみてはいかがでしょうか。G検定の運営元のJDLA公認、また東京大学教授の松原氏が監修する講座となっており、市販のテキストやインターネットでは得られない高度な知識を手にすることが可能です。
また不明点はチャットや音声通話を通じ、講師に自由に質問することができるため、圧倒的な学習効率を実現しています。「プログラミングスクールは高額で手が出せない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
ここまでG検定のおすすめテキストや選び方、学習方法についてご紹介してきました。G検定のテキストはなるべく日本ディープラーニング協会(JDLA)公式のものを選ぶこと、また発刊日が新しいものを選ぶことがコツです。
また効率のいい勉強を行うなら、テキストは別売りの問題集と併用し、アウトプット中心に学習することが大切になります。テキストが難しければインターネット教材やスクール、また「JDLA認定 G検定対策講座」など、さまざまな選択肢があります。
自分に合った手段を選び、G検定の対策を効果的に進めていきましょう。