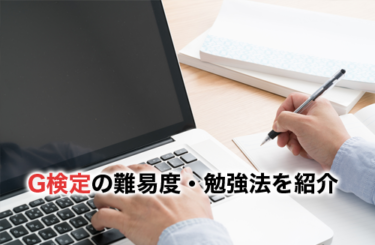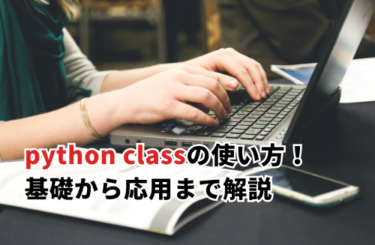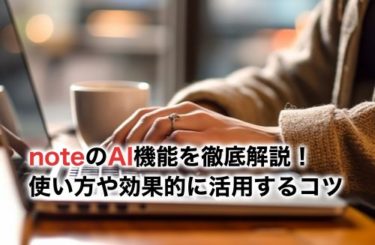これまで人間は小説などの文章を書く際に、自分の頭で考えて執筆を行っていました。
しかし、AIの登場で小説をAIが執筆する事が可能となり、なんとAIが執筆した小説が文学賞を受賞したのです。
第1回「AIのべりすと文学賞」を受賞した作品は、日本のSF作家である高島雄哉氏がAIを用いて執筆した小説「798ゴーストオークション」で、日本初となるAIによる文学賞は世間に衝撃を与えました。今後もAIを用いた小説が文学賞を受賞する機会が増えていく機会が増えるでしょう。
では、AIで小説の執筆を行うには具体的にどうするのでしょうか?
今回は、小説AIの仕組みやサービスの選び方、AIによる小説の自動生成が可能なサービスサイトをご紹介します。
AIが小説を執筆する仕組みとは?
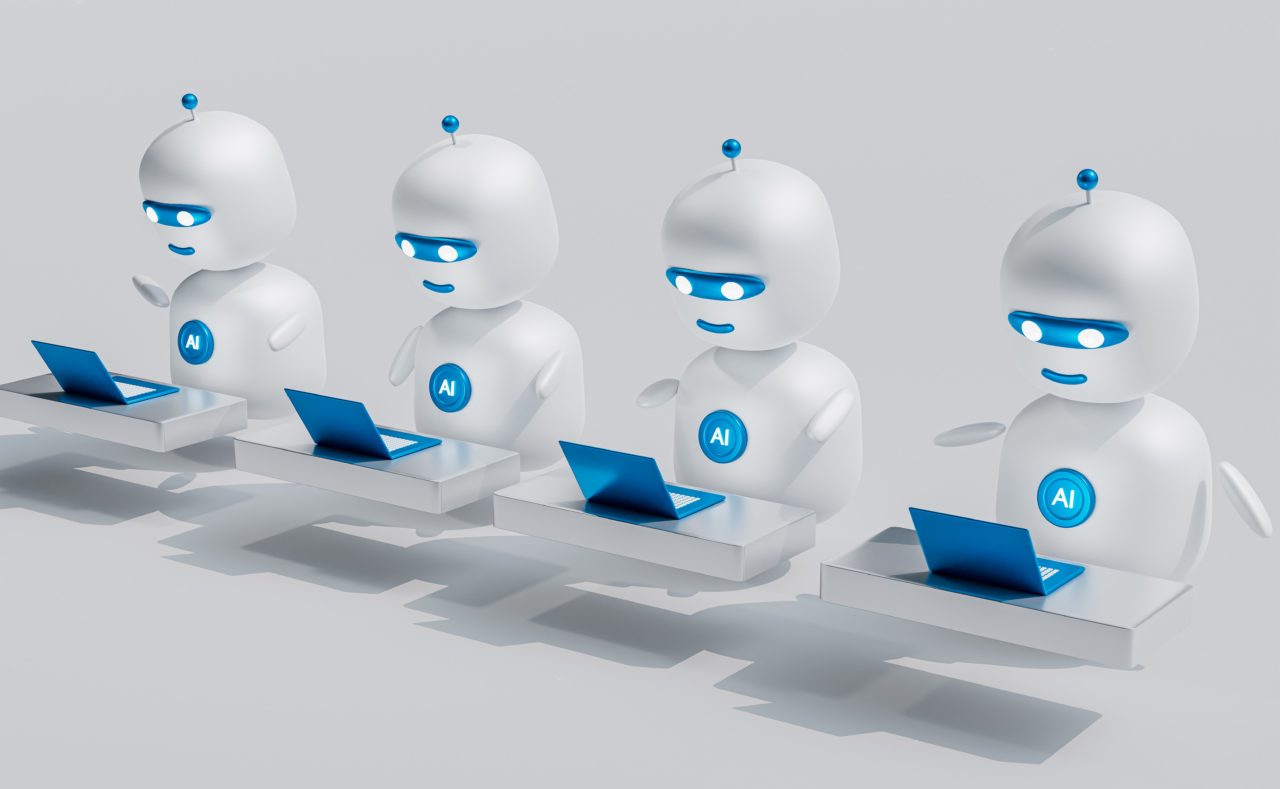
まず最初に、AIが小説を執筆する仕組みについて紹介します。小説をAIが執筆する仕組みは、3つに大きく分類されます。
1.既存のテキストを組み合わせる
AIは大量のテキストデータを学習しており、学習したデータの中から必要な単語やフレーズを抽出します。小説をAIが執筆する際は、複数のテキスト同士を切り抜いて貼り付けるように組み合わせて文章を生成しています。
2.文章の構成からテキストを生成する
既存のテキストの組み合わせでは、文章が単調になりやすく独自性がないというデメリットがありました。そこで、人間が土台となる小説の構成や文脈の基本を執筆する事で、AIがその文章の構成や文脈を理解し、新しい文章を生成する方法を提案します。
これにより、独自性のある自然な文章を作成する事が可能となるのです。
3.物語の筋・文章生成を機械化する
最近では、物語の筋(プロット)と文章の生成を機械化する方法を使用する方法が多くなりました。小説をAIが執筆する際は、プロットの作成と文章の作成をAIがそれぞれ担当します。
プロットの生成を行うAIは、物語の筋や登場人物の行動を生成します。
その生成されたプロットを基に文章生成担当のAIが文章を作成するのです。
この方法により、AIがより高度で複雑な小説を執筆する事が可能になります。
小説をAIが執筆するメリット
小説AIを活用し、小説をAIが執筆するメリットを紹介します。
作業の効率化を図れる
小説AIは、人間が文章を執筆する場合と比較すると、より速く短時間で多くの文章を作成します。例えば、一般的なAIの場合、1000文字程度の文章はわずか数秒で作成が可能です。
また、人間のように手や頭を動かす訳ではないため、物理的に疲労も感じません。
人間では不可能な365日24時間の稼働が可能なため、作業の効率化を図る事が出来るのです。
アイデア出しのヒントをもらえる
小説AIサービスは、大量のテキストデータを学習しているため、様々なアイデアを生成することが可能です。例えば、小説をAIが執筆する際にも以下のような創作のヒントを得られるでしょう。
- 物語の筋書き
- 世界観などの設定
- 登場人物の設定
さらに、既存の小説や映画などからアイデアのヒントを抽出・分析する事も可能なため、新たな視点や発想が加わり、予想外の見解や人間が思いつかないような考え方を見つける補助ツールにもなります。
小説をAIが執筆するデメリット
小説AIを使用する上で、小説をAIが執筆するデメリットを紹介します。
著作権侵害の恐れがある
AIは大量のテキストデータを学習し、そのデータに基づいて文章を生成します。
そのため、指示を出して執筆した小説の内容が既存の作品と類似する可能性も考えられます。
既存の作品と類似性や依拠性が認められたAIが執筆した小説を利用すると、著作権侵害に当たるため、活用する際は必ず確認を行うなどの対策が必要です。
AIによる小説の自動生成が可能なサービス・サイト3選
初めて使用する方でも簡単な小説AIによる自動生成が出来るサービスをご紹介します。
各サービスの特徴や機能面、登録の簡単さなども確認してください。
1.AIのべりすと
引用:AIのべりすと
日本のゲームクリエイターであるSta氏が開発・運営を行っている小説AIサービスです。
無料版でも利用可能で、登録も不要です。
一般的なAIは、ChatGPTのように英語の言語モデルを用いて学習しますが、AIのべりすとは日本語の言語モデルを用いて学習を行います。
膨大な日本語データをまとめた約500GBのテキストデータセット(コーパス)を基にしているため、自然で違和感の少ない高度な文章の作成が可能です。
従って、人間がわずか数行の文章を書き出す事で、AIがその先の物語を自動作成します。
自動生成した文章を用いて、人間が新たな文章を入力する作業を繰り返すと、長編の小説も簡単に生み出せます。
また、書き出しの文章の設定を変更する事により、物語の展開も変更可能です。
AIのべりすとには有料版もあり、生成回数が無制限、詳細設定が可能というメリットがありますが、最初は無料版の使用で十分でしょう。
また、作成した作品は無料・有料問わず、商用利用ができます。
2.AI BunCho
引用:AI BunCho
AIのべりすと同様に、個人クリエイターである大曽根宏幸氏が開発・運営を行っているシナリオ作成AIサービスです。AI BunChoはユーザー登録が必要ですが、無料版であっても生成回数は無制限という利点があります。
AI BunChoは、60億のパラメータを持つ日本語の言語モデルで、小説に特化して学習を行っているため、物語の生成を得意としています。そのため、アニメや動画などの物語のベースとなる話も作成可能です。
従って、自分が作成した作品の他に既存の作品の二次創作としても利用できるでしょう。
AI BunChoは、「AIリレー小説」といったAIと人間が共同で物語を作成する機能が特徴的です。
人間が本文入力エリアに文章を入力すると、その先の物語をAIが作成する仕組みは、AIのべりすとと同様です。
しかし、あらかじめシナリオ設定で物語の世界観の設定を行う事で、AIが作成する文章の世界観の制御が可能になり、人間の思い通りの文章を作成しやすくなります。
また、想定されるキーワードを入力すると物語の設定や全体像からタイトルを生成する機能などもあります。
3.Canva
引用:Canva
無料で利用可能なオンラインのグラフィックデザインツールです。
新規会員登録を行うか、Googleアカウントなどでログインを行うと利用可能になります。
有料版は生成回数が無制限といった利点がありますが、無料版であっても25回は生成可能なため十分でしょう。
Canvaは2022年末に、Canva DocsといったGoogleドキュメントに類似したサービスを開始しました。Canva Docs内のMagic Writeストーリージェネレーターは、Chat GPT APIを搭載しており、2021年半ばまでのデータを用いて学習しています。
これにより、Magic Writeが自動で文章を作成する仕組みです。
ストーリージェネレーターは上記の2つのサービス同様に、人間が簡単なプロンプトの入力を行うと、AIがその続きを執筆する共同作業で物語を作成します。
なお、入力された既存のテキストにキーワードを追加するとAIがアイデアを出し、新しい物語を作成する事も可能です。
ストーリージェネレーターツールは共有可能であるため、複数人でのストーリーの執筆もできます。また、執筆中の物語にText to Imageといった機能を活用する事で、ストーリーに沿ったイメージを伝える画像の作成も可能です。
小説の表紙などデザインの作成を行う際にも、別のツールを使用せず、Canvaのみで視覚的なデザインを作成する事ができます。Canvaは、パソコンの他にスマートフォンなど様々なデバイスで利用できるため、作業の効率化を図れるでしょう。
小説AIサービスの選び方
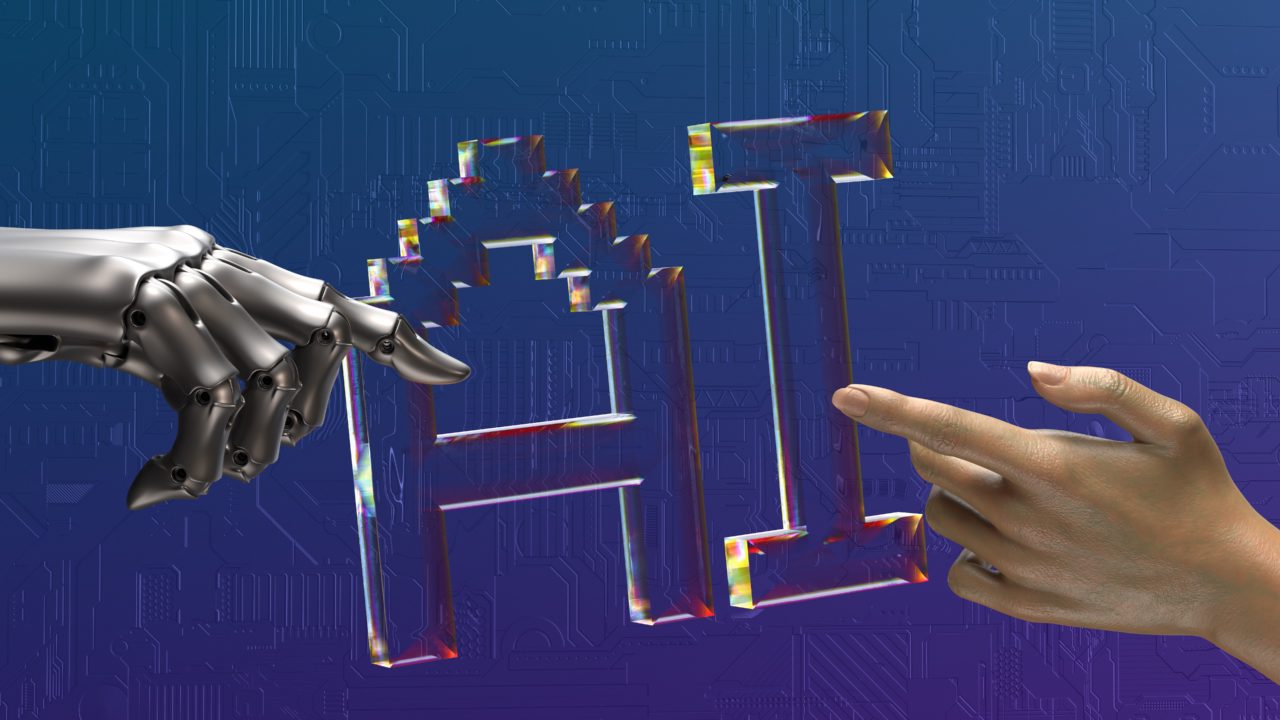
小説をAIが執筆するサービスには様々な種類があるため、どんなサービスを使用すれば良いか迷う方もいると思います。AI小説サービスの選び方について詳しくご紹介します。
登録の簡単さ
小説AIサービスを選ぶ際は、登録が簡単かどうかを確認します。
小説AIサービスには、登録が必要なサービスと登録不要なサービスがあります。
登録が必要な場合に本人確認などの会員登録が面倒と感じたら、登録不要なサービスが良いでしょう。なお、複数人でビジネス活用する場合は作業環境の安全性を確保するため、無料のサービスの使用は控え、有料のサービスの選択をして下さい。
執筆に特化した機能面
小説AIサービスを選ぶ際は、小説生成が円滑に行える機能が備わっているサービスかどうかを確認しましょう。AIが小説を執筆する際は、必然的に長い文章になります。
執筆段階で、誤字脱字や表記ゆれ(表記のばらつき)が確認できる校正機能が備わっていると効率的に作業を進められるため便利です。
利便性はシンプルに
AIが執筆を行う中で文章量が多くなると、小説AIサービスサイトの動作が重くなる可能性もあります。機能面が充実しているサービスサイトほど、動作が重くなる傾向にあるため、初めて使用する場合は、可能な限り必要最低限の機能が備わったサービスの選択をお勧めします。
小説ではなく、AIで絵を自動生成したいと思っている人はこちらの記事も参考にしてください。
小説AIで自動の小説家に挑戦しよう!
今回は、小説AIの仕組みやサービスサイトの選び方、メリット、デメリット、AIによる小説の自動生成が可能なサービスサイトをご紹介しました。
AIが人間の力を借りずに自らの力で小説を自動で執筆するまでは、まだ技術的にハードルが高いようです。
しかし、小説AIサービスを創作活動を行う際の補助ツールとして活用するのであれば、自分が思いつかない発想や視点を見出すヒントにもなります。
ぜひ、今回ご紹介した小説AIサービスを活用し、創作活動を行ってみてください。
小説AIサービスを有効活用する事で、創作活動の幅を広げられるでしょう。
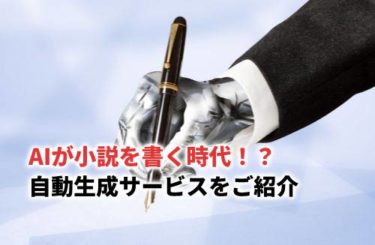
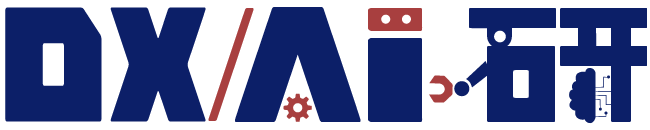
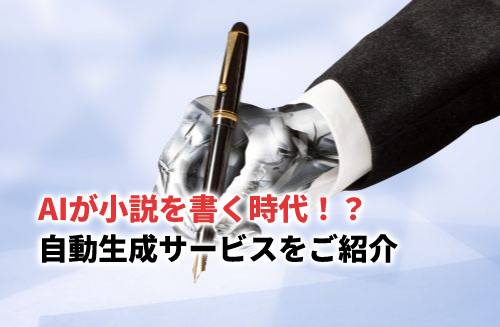
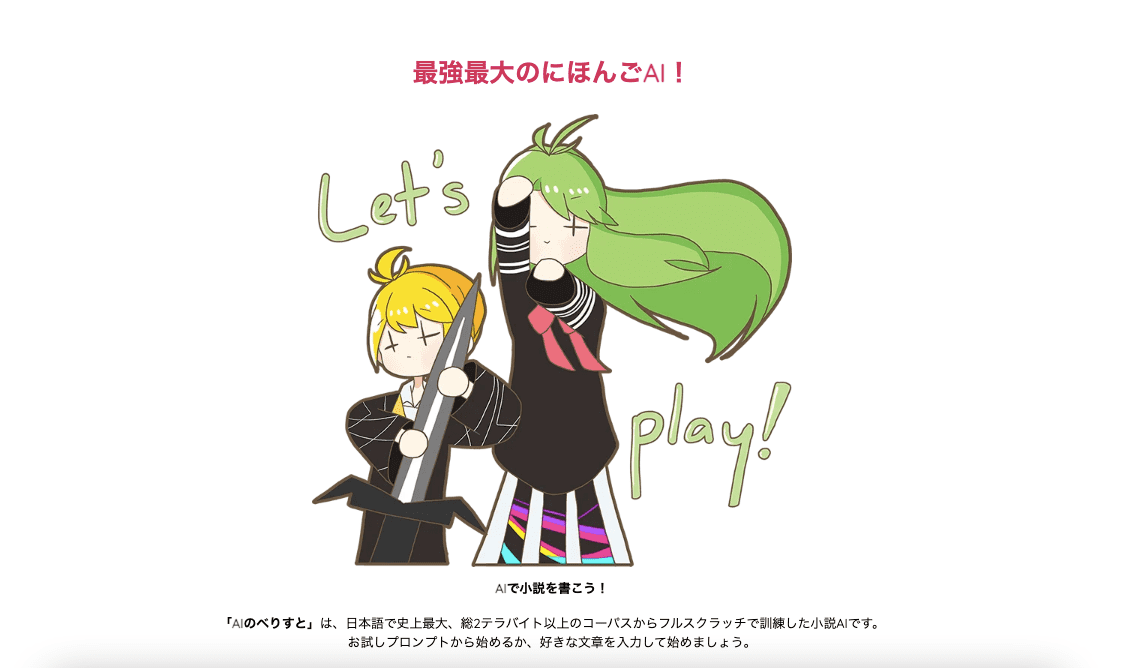
 引用:
引用: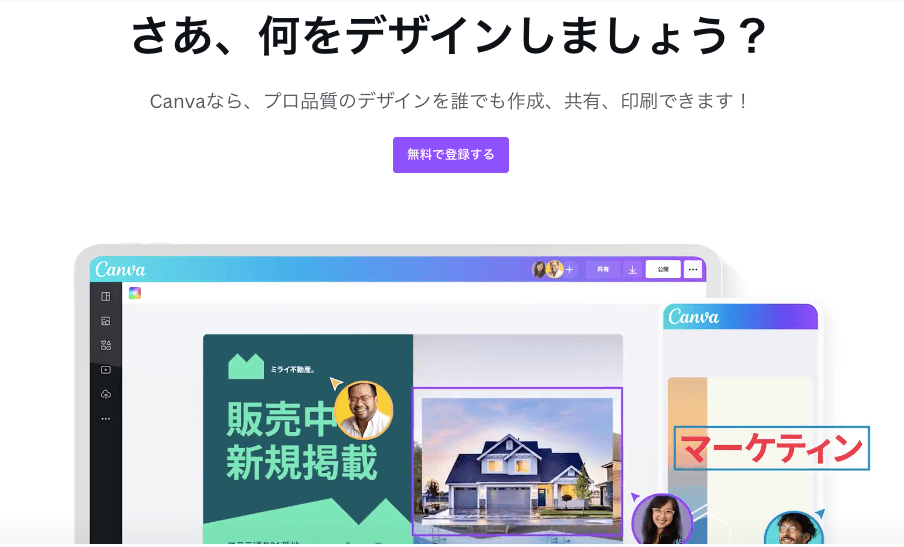 引用:
引用: