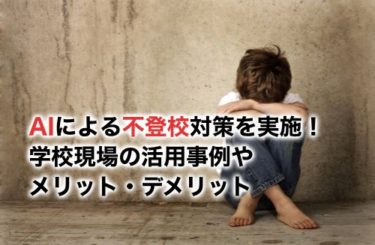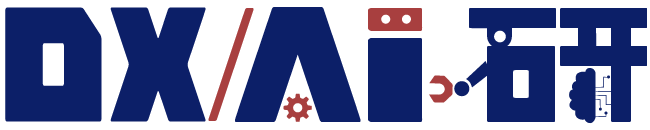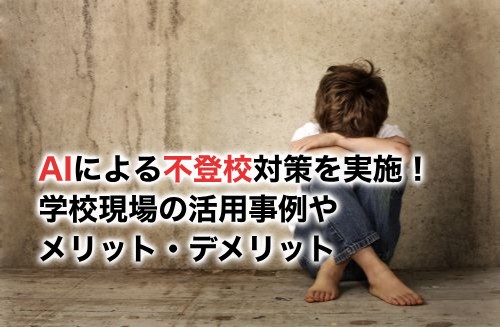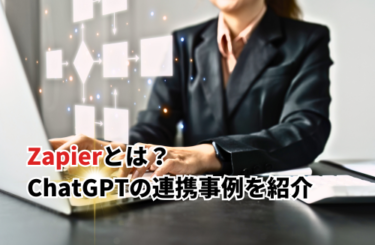埼玉県戸田市では2023年11月から2024年3月末まで、AIを活用した不登校予測モデルの構築実証事業を実施しました。この取り組みは、こども家庭庁の「こどもデータ連携実証事業」として、内田洋行氏とPKSHA Technologyグループと連携して進められたものです。
事業の目的は、学校現場での「プッシュ型支援」につなげるための不登校リスクモデルを構築することでした。文部科学省によると、小・中学校での不登校児童生徒数は、現在約30万人いるとされています。
具体的には、不登校の兆候がある児童生徒をいち早く把握し、教員が事前に支援を行い、教員が支援のきっかけを得られるようにするためです。戸田市内の公立小学校12校と中学校6校の児童生徒約1万2000人が対象となり、学校名や学年、氏名などと「不登校リスクスコア」を表示します。
リスクスコアは色分けされ、不登校のリスクが高いと赤で表示し、授業の理解度などのアンケート結果などを確認してプッシュ型支援に繋げる仕組みです。文部科学省でもCOCOLOプランという不登校対策を発表し、AIを活用した不登校生徒を救う取り組みが行われています。
今回はAIによる不登校対策の仕組みやメリットデメリット、事例を解説します。
不登校対策COCOLOプランとは

COCOLOプランは2023年3月に文部科学省が策定した不登校問題解決に向けた取り組みです。「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策」としており、以下の3つの柱を基盤としています。
- 学びの場を確保して環境を整える
- SOSを可視化して支援する
- 学校風土を改善する
上記のようなCOCOLOプランを解決するために、現在は様々な企業でAIを用いた可視化のサービスを提供しています。
AIで不登校の兆候が把握できる仕組み
AI技術の発展で従来ではアンケート調査や面談では把握が難しかった、子供たちの心の変化や潜在的な悩みを早期に発見することが可能です。では、具体的にAIはどのようなデータから生徒たちの不登校の兆候を把握するのでしょうか。
AIシステムにより必要なデータは異なりますが、主なデータは以下のようなものです。
| データ | データ内容 | 効果 |
| 学習データの分析 | 過去の学習記録やテスト結果、学習時間 | 学習意欲の低下や理解度の低下の兆候を発見 |
| 行動データの分析 | 校内での行動データ | 引きこもりやいじめなどの兆候を発見 |
| 生理データの分析 | 体温、健康状態などのデータ | ストレスや体調不良などの兆候を発見 |
AIによる不登校対策のメリット

AIによる不登校対策にはどのようなメリットがあるのでしょうか。具体的に以下で解説します。
不登校の早期発見や対策ができる
AIは膨大な量の生徒のデータを分析することで、不登校リスクの高い子供たちを早期に発見することができます。そのため、教員が早期から個別支援を行うことができ、不登校状態の長期化を防ぐことにつながるのです。
例えば、生徒たちの過去の出席状況や校内での行動パターン、SNSの投稿内容などを分析します。分析結果から生徒たちの心の負担を軽減し早期に適切な支援を受けることで、不登校を克服し、学校生活を楽しむことができるようにサポートします。
また、AIが分析したデータを基に、より効果的な個別支援を行うことができるため、教員の負担軽減にも貢献することができるでしょう。
生徒が安心して相談できる環境が作れる
AIは24時間365日の対応が可能なため、生徒が時間や場所の制約を受けずに相談することができます。AIが生徒の言葉に対し、共感を示しながら自然な会話で話を聞いてくれるため、安心して話しやすく、誰にも打ち明けられない悩みを相談しやすくなります。
そのため、客観的なデータに基づいたアドバイスを提供したり、必要な支援機関へ繋げたりすることができます。
客観的な判断ができる
AIは従来のような教員の主観や経験に頼らず、客観的なデータに基づいて判断することができます。従来のアンケート調査や面談では、子供たちの心の声を正確に把握することが難しい傾向にありました。
しかし、AIは膨大な量のデータを分析することで、潜在的な悩みや心の変化を客観的に捉えることができ、不登校リスクの高い子供たちの見逃しを防ぐことが可能です。
AIによる不登校対策のデメリット
AIによる不登校対策は、まだ発展途上段階にあります。そのため、メリットがある一方でいくつかのデメリットも存在します。以下で詳しく見ていきましょう。
プライバシーの侵害や情報の漏洩
AIによる不登校対策では、生徒の氏名や学校生活記録、健康状態、家庭環境、行動履歴など、膨大な量の個人情報が収集・分析されることがあります。適切な不登校予測を行うために重要なデータですが、適切な管理を行わないとAIシステムがハッキングされたり、不正利用されたりして生徒の個人情報が漏洩し、深刻な被害につながる可能性があるでしょう。
そのため、プライバシーの侵害を恐れずに積極的な情報収集を進めるべきか、個人の権利を尊重しながら限られた情報に基づいて判断すべきか、難しい選択を迫られます。
判断過程の信頼性の低下
AIは複雑なアルゴリズムに基づいて判断するため、判断過程の根拠が明確でなければ、教員は適切な支援を行うことができません。また、AIが誤った判断をすると、生徒に精神的な負担を与える可能性もあります。
判断過程がブラックボックス化すると、なぜそのような判断をしたのかを説明することができません。そのため、教員や保護者がAIの判断を信頼しにくくなる可能性があるでしょう。
教員が児童生徒と直接関わる機会が減少
AIによる不登校対策に頼りすぎると、教員が児童生徒と直接関わる機会が減少してしまうという懸念も生まれています。教員と児童生徒の信頼関係構築は非常に重要です。
お互いの理解と共感に基づいた関係がなければ、不登校予測に対して効果的な支援を行うことはできません。そのため、AIはあくまでもツールとして運用し、教員が児童生徒と直接会話する機会を設け、コミュニケーションを促すことが重要です。
高額な初期費用が必要
AIシステムの導入には、高額な費用がかかります。そのため、全ての学校がAIシステムを導入できるわけではないため、学校により不登校対策の格差が生まれる可能性があります。
AIシステムの種類にもよりますが、導入には、ハードウェアやソフトウェアの購入、システム構築など、様々な費用がかかります。AIシステム本体の費用は高額であり、多くの学校にとって大きな負担となるでしょう。
また、導入しただけでは、効果的な不登校対策を実現することはできません。システムの運用には、データ学習費はもちろん、メンテナンス費用などの継続的な費用がかかります。
AIによる不登校の兆候を診断した事例
文部科学省が策定したCOCOLOプランは、不登校問題の解決に向けた大きな一歩として期待されているものの、現場の教職員にとって、多忙な業務に加えて新たな施策を実行することは大きな負担です。そのため、先述したようにCOCOLOプランをスムーズに実施できるように様々なツールが提供されています。
以下でそのサービスの一部を紹介します。
生徒エンゲージメント可視化サービス
NECネッツアイ株式会社では、COCOLOプランの実現に向けて、AIを活用した生徒エンゲージメント可視化サービスを提供しています。学校生活における生徒の行動や心理状態をAIで可視化することで、不登校の早期発見・早期支援に役立てることを目的としています。
具体的には、AIチャットボットとの対話形式で生徒に毎日の気持ちを入力してもらい、一人ひとりの心の変化を可視化します。教員は生徒の心の変化を把握し、メンタルケアをサポートして未然にトラブルを防ぐ仕組みです。
また、AIチャットでは気持ちの入力以外にも以下のような機能があります。
- 誰にも話しにくい内容をチャットボットと会話できる
- 困っていることを先生だけに打ち明けることができる
悩みチャット相談システムの導入
AIによるカウンセリングサービスの開発を行う株式会社ZIAIは、東京都立桐ヶ丘高等学校にて、AI技術を活用した「悩みチャット相談システム」の導入・運用を開始しています。これは東京都教育庁と連携し、増加傾向にある不登校やひきこもりなどの子供たちの悩みを早期発見・解決することを目的とした取り組みです。
悩みチャット相談システムは、東京都の「スタートアップによる事業提案制度」採択プロジェクトの一環として実現しました。桐ヶ丘高等学校の生徒を対象に、AIが生徒一人ひとりの悩みに寄り添い、安心して相談できる環境を提供するようです。
一人ひとりに寄り添った支援体制を構築
佐賀県みやき町教育委員会は、2023年4月からAIによる診断システムを導入し、不登校や虐待など支援が必要な児童生徒を早期発見・支援する取り組みを開始しています。九州初の試みとして注目を集めていました。
導入されるAI診断システムは、大阪公立大学の研究者により収集されたデータを基にしており、児童生徒一人ひとりの状況を20項目程度入力することで、不登校などの兆候を診断します。診断結果は、学校での対応や児童相談所などの専門機関への連携の判断材料として活用されているようです。
教職員による日々の観察に加え、AIを活用することで小さな兆候も見逃さず、児童生徒一人ひとりに寄り添った支援体制を構築することを目指しています。
AIによる不登校対策で一人ひとりに合ったサポートが可能に
今回はAIによる不登校対策の仕組みやメリットデメリット、事例を解説しました。AIは不登校の問題解決に有効なツールとなり得る一方で、プライバシーの侵害や高額な初期費用など、克服すべき課題も多く存在します。
AIを過信することなく、生徒一人ひとりに寄り添った支援を常に念頭に置くことが重要です。AIによる不登校対策は客観的なデータに基づき、生徒たちの学校生活における様々な課題に対応し、支援を提供するという大きな可能性を秘めています。
関係者一人ひとりが力を合わせ、生徒たちが安心して学べる環境を実現していきましょう。